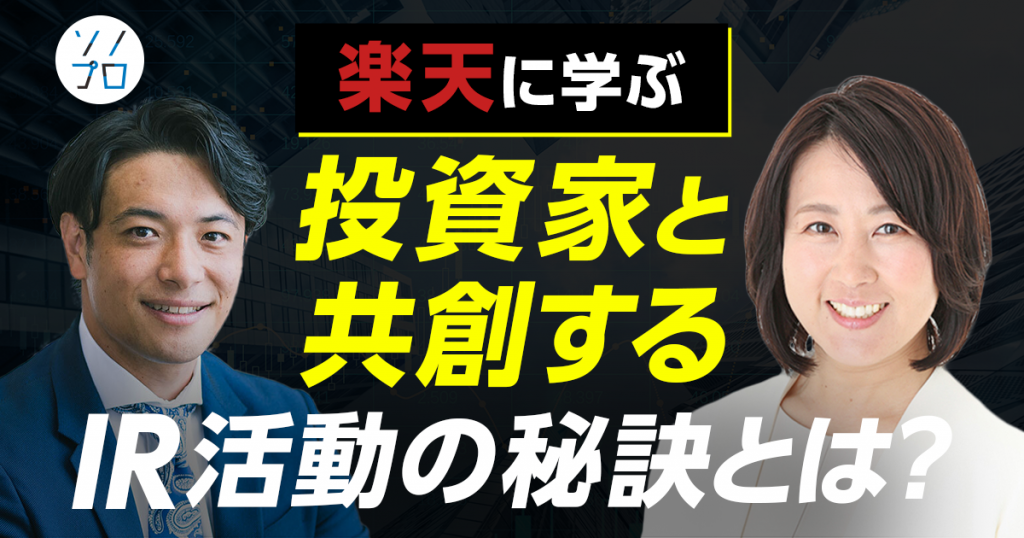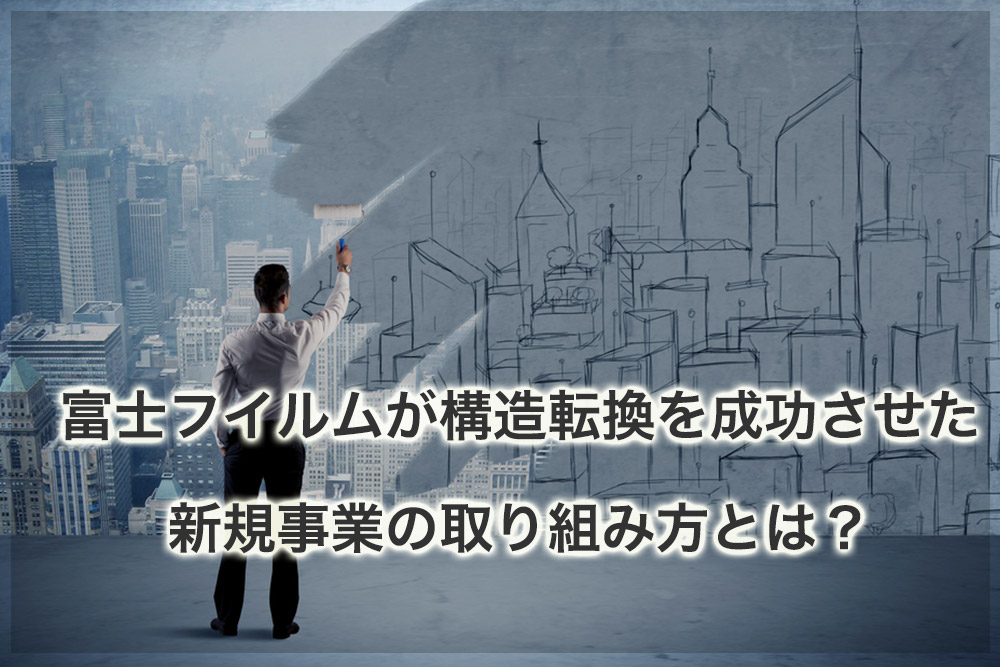【資本政策】会社の価値はどのように決まるのか?企業価値の評価

資本政策コラムの第5回は、企業価値の評価についてです。会社の価値とはどのように決まるのでしょうか?
「この業界はPER25倍くらいだよね」などという言葉を耳にすることもあると思いますが、どういう意味でしょうか。奥の深い企業価値算定の世界、専門的なことを掘り下げるときりがないですが、まずは初歩的な事を解説いただきました。
Contents
あらゆる資本政策を検討するにあたって必要となるのが「会社の価値」
普通株で増資をするにも種類株で増資をするにも、ストック・オプションを発行するにも、M&Aをするにも、あらゆる資本政策を検討するにあたって必要となるのが「自分の会社が今いくらなのか?」ということです。
資本政策上、株価をどう設定するかの重要性はこれまでのコラムでも説明してきましたし、実務上の経験として理解されている方も多いかと思いますが、改めて、第1回目のコラムで掲載した、資本政策のよくある失敗例の一部を再掲させていただきます。
- 上場前の株式譲渡での後悔
上場予定時期の2年前に、貢献してくれた従業員や取引先、親族に報いるため株式を低廉な価格(根拠のない低い価格)で配ったが、その価格の根拠を上場審査で説明できず、上場スケジュールの見通しが立たなくなった。その後上場できなくなったにもかかわらず、後日、税務調査があり、株式を売却していない従業員たちが思いがけない多額の税金支払を求められ迷惑をかけてしまった。
- 上場前の新株発行による資金調達での後悔
上場準備初期段階で身の丈に合わない高い株価でファイナンスをしたが、その後、前回の株価水準によるファイナンスでは応募者がなく、株価を下げた価格でのファイナンスを実行しようにも、既存株主から反対を受けてしまい実行できなかった。このような状況から資金繰りも苦しくなり、上場を考える余裕がなくなってしまった。
株価は、時価よりも高くても低くても問題が発生するのです。
株価がわからないと、適切な意思決定ができません。
プロの投資家から提案を受けた株価で漫然と意思決定をすることが、本当によくありますが、大きな誤りのもととなります。そこで今回は株価を図るモノサシを提供するべく、「会社の値段の決まり方」について説明します。
「会社の値段の決まり方」理論
企業価値評価の理論は大別すると次に述べる3つ、①ネットアセットアプローチ、②マーケットアプローチ、③インカム・アプローチになりますが、専門的なことを掘り下げるとどれだけ時間を割いても足りないので、できるだけ感覚的に理解できる範囲に留めることをご了承ください。
①ネットアセット・アプローチ:わかりやすいが・・・
まず、最初に「時価純資産法(ネットアセット・アプローチ)」を紹介します。
この方法は、企業が保有する資産をすべて売却したと仮定して得たキャッシュから、買掛金や借入金などの債務を差し引いて残ったキャッシュがいくらになるかで判断する方法です。
この方法は資産負債の時価さえわかれば足し算引き算で計算でき、わかりやすいのですが、対象企業を清算するとか、長期的に利益があがらず清算の可能性があること等が前提になるため、一般的なM&Aにおける評価では用いられません。
株価は将来どの程度成長するかの期待値に対して付けられるのであって、今清算したらいくらになるか、に付けられるのではありません。この感覚は、成熟企業よりもむしろベンチャー企業の方がおわかりいただけるかと思います。
②マーケット・アプローチ:市場は常に正しいか・・・
次にわかりやすいものとして、マーケット・アプローチを紹介します。
この方法を簡単に言うと「類似の商品がいくらで売られているのか」を基準に価値を算出します。例えば、自分が住むマンションの、広さや間取りがほぼ同じ隣の部屋が4,000万円で売られていることが分かれば、自分の部屋もそれに近い金額で売れるのではないかと類推できるでしょう。
マーケット・アプローチの代表的な手法は「市場株価法」であり、実際に評価対象企業が上場している場合、その株価を参照します。
一方、評価対象企業が非上場の場合、上場している類似企業の株価を参照する方法があります。対象企業と同じ業種で同じような利益を出している企業があれば、企業価値はほぼ等しいはずだ、というのが考え方の基礎です。この方法を「類似会社比較法(マルチプル法)」と呼びます。
よくベンチャー企業においても、「この業界はPER25倍くらいだよね」といった会話がなされることがありますが、これは類似会社比較法の発想に基づいています。なお、念のため、PERとは株価収益率であり、時価総額が純利益の何倍となっているかという指標です。
一見客観性が高そうなマーケット・アプローチですが、弱点もあります。それは、「市場がいつも正しい」とは限らないことです。市場は企業の正確な実態をいつも反映して動く訳ではありません。特に短期的には。投機的な取引による株価の乱高下もあれば、バブルやリーマンショック、先日のチャイナショックという社会や経済現象、東日本大震災のような天災による混乱は皆さんにも実感がおありかと思います。
また、ベンチャー企業においては、特に設立後間もない場合、上場まで漕ぎ着けた会社と比較しても参考にならないこともありますし、新規性の高い事業を行うベンチャー企業は類似の事業を行う会社の選定が困難であることもしばしばです。
③インカム・アプローチ:要は将来いくら稼ぐ可能性があるか
3手法の最後は、「収益還元法(インカム・アプローチ)」です。代表例はDCF法(Discounted Cash flow法)で、ごくごく簡単に言うと、「将来のキャッシュフロー÷期待利回り」で企業の価値を算出するものです。
再度マンションの例を挙げます。年間の家賃として200万円が想定できる部屋の期待利回りが5%であったします。DCF法では、その部屋の価値は200万円÷5%=4,000万円と導かれることになります。企業価値を算出する場合、その企業が将来生み出す予想キャッシュフロー(フリーキャッシュフロー)を、その企業に投資する株主などが期待している利回り(資本コスト)で割れば良いわけです。
この方法は、マーケット・アプローチのように市場からの影響を受けることなく企業の実力を反映させた価値算定が可能と考えられるため、企業の真の価値を算出するのに一番適した方法といえます。
ベンチャー企業が上場時や上場前に資金調達を行う局面で、成長可能性について徹底的にインタビューを受けることになりますが、それは、このインカム・アプローチの発想からくるものです。
DCF法はもろ刃の剣
DCF法にも弱点はあります。DCF法は使い方によって評価結果に大きな差異が発生してしまいます。将来のキャッシュフロー予想を非現実的な程に楽観的に設定したり、資本コスト(リスク)を過小評価したりすれば企業価値は過大評価されてしまうことになります。また、反対に、将来キャッシュフローの妥当性を投資家に評価してもらえなかったり、資本コストを過大に評価されたりすれば、企業価値は過小評価されてしまうことになります。
例えば、起業ほやほやのベンチャー企業の社長が増資をするべく、自社の株式価値を算定する局面を考えてみましょう。野心的な社長であればあるほど、将来業績に対し、過大な見積もりをしてしまうものです。
例えば、売上目標について、来年は5億円、再来年は50億円、3年後は100億円などと見積もれば、DCF法による株式価値は青天井になります。非現実的な前提で算定した株価で増資に応じてくれる投資家はまずいないため、この株式価値は公正なものとはいえません。売上目標という将来予想について、できるだけ精度が高く、客観的な説得力があるものとする努力が求められるのです。
なお、この失敗例がオリンパス事件です。本業とは関連の薄い、売上高数億円しかない国内3社を、なんと700億円以上で買収し、その後の決算で500億円以上の減損処理を行ないました。この算定を行った公認会計士も、詳細資料の提供もなく、経営者インタビューも行えない等の、算定過程の異常性について、疑いを持ちながらも黙認していたことがわかっています。
当然のことですが、企業価値評価に関わる人間は、与えられた情報を鵜呑みにせず、機械的な算定作業をせず、把握でき得るすべての情報について充分な検討と吟味を加え、かつ種々の状況を勘案し、慎重かつ細心の注意をもって算定業務をしなければなりません。
重要なのは事業計画
ここまでのまとめですが、客観的且つ合理的な前提で作成された事業計画が、会社の価値を説明する根幹になるわけです。
いかに新規性の高い事業を行うベンチャー企業といえど、必要になるのは、抽象的な売上目標ではなく、合理的なKPIを積み上げて作成し、経営者自らが説得力を持って説明することができる事業計画です。
ところで、このコラム連載で、事業計画という言葉が出てくるのは2回目になります。初回の「資本政策とは」の回で、「資本政策の根っこである事業計画」として説明しました。すなわち、事業計画は、資本政策の根っこであり、株価の根幹であり、株価は資本政策の最重要項目ですから、事業計画(資金計画)-資本政策-株価は三位一体であり、すべては事業計画から始まるのです。
<関連記事>
- 【種類株】普通株以外での増資で創業オーナーと投資家の悩みを解決。種類株の活用
- 資金調達を考えるためのステップ ベンチャー企業にとってVCとつきあうことの意味【後編】
- 資金調達を考えるためのステップ ベンチャー企業にとってVCとつきあうことの意味【前編】
- 起業家はIPOを目指すのが正解なのか?非上場会社のメリット
監修:山田 昌史氏
株式会社プルータス・コンサルティング 取締役マネージング・ダイレクター 米国公認会計士
組織再編・有価証券発行・資本政策関連のアドバイザリー業務、有価証券の設計・評価業務、企業価値評価業務に従事し、多数の案件を手掛ける。企業研修・大学MBA講師。企業買収に係る第三者委員も務める。具体的プロジェクトには、TOB、株式交換等の組織再編アドバイザリー、資金調達アドバイザリー、非上場会社の資本構成の再構成コンサルティング、インセンティブ・プラン導入コンサルティングなどがある。
著書に「企業価値評価の実務Q&A」(共著、中央経済社)、旬刊商事法務No.2042、2043「新株予約権と信託を組み合わせた新たなインセンティブ・プラン」(共著)、ビジネス法務第19巻第4号「法務担当者のための非上場株式評価早わかり(第4回)」(共著)、企業会計Vol.68No.5「制度の変遷で理解する株式報酬諸制度のメリット・デメリット」、旬刊経理情報No1402「時価発行新株予約権信託の概要と活用可能性」(共著)、No1395「業績連動型新株予約権の設計上の留意点」(共著)掲載などがある。
2019年8月より京都大学経営管理大学院の客員教授に。